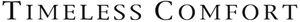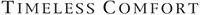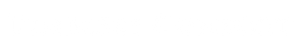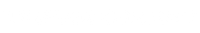映画の中に登場する家具やインテリアに注目し、その物語との関係を紐解くコラムの第2弾。今回は来月2月3日に公開のフランス映画が題材です。
『すべてうまくいきますように』はフランスのフランソワ・オゾン監督が長年交流してきた作家、エマニュエル・ベルンエイムの自伝的な小説を映画化したものである。
ふたりは『スイミングプール』(2003)、『ふたりの5つの分かれ路』(2004)で監督と脚本家としてコラボレーションを行い、ベルンエイムの生前、彼女自身の体験をもとにしたこの物語を聞いていたという。
それは、人生を謳歌してきた84歳の父親が脳卒中で倒れ、入院して早々、娘に「終わらせてほしい」と自分の安楽死の実現化を依頼する物語である。当初からオゾンはベルンエイムに映画化を託されたが、話を聞いた当初はどうやってじぶんのものにするのかわからず、彼女が亡くなり、自身の年齢を重ねたことからようやく映画化に取り組むことができたという。
ベルンエイムを投影するヒロイン、エマニュエルを演じるのはソフィー・マルソー。50代の作家である彼女はある日、父親が倒れたとの報を聞き、病院に駆けつける。父アンドレ(アンドレ・デュソリエ)は一代で財を成した実業家で、現代美術のコレクターとしても名を馳せた人物である。母親クロード(『スイミングプール』の魅惑的な作家を演じたシャーロット・ランプリングが演じている)は著名な彫刻家だったがパーキンソン病と鬱を患い、長い間、父親とは別居生活を続けている。

オゾンは、思いもよらぬ出会いと別れを描いてきた達人である。
今作は親族の別れが題材になっていて、そう聞くと、沈鬱なトーンを思い描きそうだが、意外にもそうならないのは、ソフィー・マルソー演じるヒロインと、妹パスカル(ジェラルディーヌ・ベラス)の決断が実にドライに、そして知性的になされていくから。
もちろん、父の死が間近に迫ったことで心は動揺するし、安楽死したいという父の願いを受け入れていいのか、そのためにはどういう手順で、法を犯すことなく、安らかに送り出すことができるのか、悩むし、正解もない。それでも姉妹たちは、父の願いに耳を傾け、彼の願いを無視したり、頭ごなしに否定するのではなく、本人の納得する終わり方を冷静に模索していく。感情的にぶつかる場面もあるが、成熟した大人たちの会話なので、常に感情過多になりすぎず、抑制した中で会話が行き来する。終末期の過ごし方は様々な選択が考えられる。今作、この一家が取った方法は潤沢な資金があるから、という身もふたもない経済状態が関係もしているが、ひとつの在り方として参考になる部分は多々見受けられる。

例えば、父の判断が鈍る前に、公証人を病室に呼んで、彼の財産を死後、どうするのかの意思確認。お世話になった人への生涯最後となる別れや挨拶をどう父は望み、どういう形で会談させるのか。親族、友人関係の中にも順列があり、ほぼ疎遠となっていても、最初の面会は別居中の母親を最優先にするように姉妹が奮闘する姿など、ふたりが死後、残された人々のこころが「こじれない」よう、意を汲み、丁寧に処理していく姿には頭が下がる。

しかも、この父がかなりの曲者なのだ。
エマニュエルは度々、少女時代の父とのやり取りを回想するが、ほぼけなされる風景しか浮かんでこない。『ラ・ブーム』でのアイドル全盛期の愛らしさを未だに強く残すソフィー・マルソーだが、今作では余裕がなく、化粧もほぼせず、という状態を演じていて、かなり苦笑する場面が多くみられる。なおかつ、父は後年、自身の同性愛をカミングアウトし、その件で母親一家を怒らせ、疎遠となった件に恨みつらみがあり、何かというとその感情が噴出してくる。姉妹が「胡散臭いやつ」と毛嫌いしている父の友人、ジェラールとの関係には、娘たちが見たくない父の顔が噴き出てくる。それでも、なお、父の望む死の在り方を模索する娘たちの奮闘はどこか前向きで、父の積極的な姿勢も加わり、なぜか明るささえ見出す行為に思わてくるのが、オゾンの演出力なのだろう。

この映画を暗くさせないもうひとつの大きな要素が、それぞれの家の瀟洒(しょうしゃ)な空間である。
エマニュエルの家には部屋の壁面いっぱいに大きな書棚があり、そこには本だけでなく、見せるためのインテリアとして、オレンジの花瓶が書棚の差し色として置かれている。エマニュエルの部屋にはいくつか赤がポイントとなっていて、彼女の仕事場を華やかに演出する。
彫刻家の母のアトリエにも大きな書棚があり、そこには自身の彫刻が美しく配列されている。こちらはグレーがベースとなったモダンな空間。また、エマニュエルが相談に行く病院にも壁面の棚があり、患者の目や心を和ます絵が飾られている。
あくまでも物語の背景にあり、今作は映画美術が主張する作品ではないけれど、昼間、重い選択を迫られる家族たちが、夜、悩み事からふと離れて、自分のペースを取り戻す空間として、書棚のある部屋たちがこの物語を支えている。
映画ジャーナリスト 金原由佳
2/3(金) ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館、Bunkamuraル・シネマ
他公開
------------------------------------------------------------------------------------
配給:キノフィルムズ
------------------------------------------------------------------------------------
© 2020 MANDARIN
PRODUCTION – FOZ – France 2 CINEMA – PLAYTIME PRODUCTION – SCOPE PICTURES
------------------------------------------------------------------------------------
監督・脚本:フランソワ・オゾン(『ぼくを葬る』『グレース・オブ・ゴッド 告発の時』)
出演:ソフィー・マルソー アンドレ・デュソリエ ジェラルディーヌ・ペラス シャーロット・ランプリング ハンナ・シグラ エリック・カラヴァカ グレゴリー・ガドゥボワ
------------------------------------------------------------------------------------
2021│フランス・ベルギー│フランス語・ドイツ語・英語│113分│カラー│アメリカンビスタ│5.1ch│原題:Tout s'est bien passé│字幕翻訳:松浦美奈│映倫区分:G
提供:木下グループ 配給:キノフィルムズ 公式HP:ewf-movie.jp

金原由佳 PROFILE
画ジャーナリスト。関西学院大学経済学部卒業後、金融の営業職を経て、映画業界へ。これまで2000人以上の映画人のインタビューを実施、キネマ旬報社発行の『アクターズ・ファイル』では、浅野忠信、妻夫木聡、永瀬正敏のロングインタビューを担当。著書に、映画における少女と暴力性を考察した『ブロークン・ガール 美しくこわすガールたち』(フィルムアート社)、共著に日本映画黄金期の映画美術を検証した『伝説の映画美術監督たち×種田陽平』(スペースシャワーネットワーク)。昨年、没後20年を迎えた相米慎二に関する共著、編集参加として『相米慎二 最低な日々』(ライスプレス)、『相米慎二という未来』(東京ニュース通信社)など。去る9月にリリースされた相米監督の『光る女デジタルリマスター修正版』Blu-rayでは、ブックレットをディレクションした。 現在、『キネマ旬報』ほかの映画雑誌、朝日新聞、『母の友』(福音館書店)、LEEウェブ版で映画評を執筆。