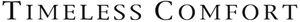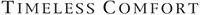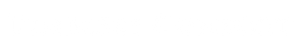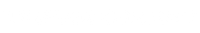話し合いを重ねることで 新しい可能性が見えてくる
-「Homeland」はデザイナーを立てずに日本全国の工場ともの作りをしていると伺いましたが、具体的にはどのように進めているのでしょうか。
永井 まず、パートナーシップを結ぶメーカーさんを見つけてくるのは多くの場合私の役目です。その後、「具体的にどんな商品に詰めていくか」というところは、玉置さんにリードしてもらっています。肉や野菜を見つけてくるのが私で、玉置さんが料理してくださる、みたいな役割分担ですね(笑)。
髙橋 最初はどうやって見つけるんですか?
永井 いろいろですね。「こんなものを作りたい」と思ったら、可能性がありそうな土地や工場さんを調べます。ホームページがあればそれをじっくり見て、「きちんとしたものを作っているかな?」と商品の写真を見たり、社長の顔写真を見たり……。「どこで売っているか」「どんなものを作っているか」「価格はどうか」も確認します。それで何社も何社も見ていると、なんとなく「このあたりのメーカーさんかな」というのが見えてくるんです。
玉置 その後、チームで直接工場へ足を運んで中を見せていただくんですよね。工場内を見るともう、だいたいのことがわかります。どんな気概でもの作りをされているのか、どんなところにこだわって作っているのか……。もちろん下調べをたくさんしてから臨むのですが、実際足を運んでみたら「違うかも」ということもあります。すべてがうまく回っている工場さんは、もうそれで完成されているからいいんですよ。ただ、今の時代に何か課題を抱えていて、「どうしようか」と迷っている、でももの作りが好きでやめられなくて……というような方たちが、私たちの提案にも「やってみようか」とお力を貸してくれることが多い気がします。だからこそ私たちが大切にしているのは、たくさんお話すること、何度も足を運ぶこと。自分たちのことや、相手の話をたくさん伺ううちに、悩みながらも「一緒にやりましょう」とおっしゃってくださる工場さんもありますし、「それはウチでは難しいけれど、○○さんのところならやれるかも」と新たな情報をいただくこともあります。
永井 何度も通いますよね(笑)。
玉置 そうなんです。もの作りは1日ではできませんから。たくさん話し合う中で、お互いに「これができるかも」「こんな可能性があるかも」みたいなこともわかってくるんですよね。例えば「Homeland」でエプロンを作っていただいている小林メリヤスさんは、長年子供服を作っていらした山梨県のニットメーカーさんです。だから、編みに関してはとても緻密な技術をお持ちなのですが、まさかキッチンツールを一緒に作るとは思わなかったとおっしゃいます(笑)。ニットでエプロン作るという発想はなかったと。でも作ってみるとニットエプロンって体にフィットして動きやすいし、伸縮性があるから肩も凝らない。実はすごく機能的なのだということに、挑戦してみたことで一緒に気づいてくださったんです。工場のみなさんも「ニットの新しい活路が見いだせました」と、喜んでくださって。
髙橋 思わぬものが生まれることもあるんですね。
永井 そこが面白いですね。小林メリヤスさんは昔から「一緒に何かやろうね」と言いながら、その「何か」がずっと見つからなかった相手なんです。今回は、「ニットのエプロンなんて売れるんだろうか」という不安を抱えつつも、色を決めて、サイズを決めて、何より彼らの最大の武器である「編み」を活かして試作を重ねた結果、とても良いものが作れました。だから、本当に皆さん喜んでいますね。


難しいことに挑戦してこそ 特別な価値がつけられる
-全国の工場との取り組みで、特に印象的だったことはありますか。
玉置 「Homeland」の最初のアイテムであるお皿や土鍋を作っていただいている、滋賀県の松庄さんとの取り組みでしょうか。松庄さんの土鍋は信楽焼なのですが、信楽焼のスカーレット(緋色)は、もともとは琵琶湖の湖底に堆積した土を調合し、松の木の灰をくべて化学反応を起こすことで出す色なんです。でも今はもうその土はほとんど残っていないし、松の木を使って作るのも作家さんくらい……という状況のなか、私たちは「昔からの緋色を再現して欲しい」とお願いしたんです。実はそれはかなり難しいことだったようで。実際にやってみたら植木鉢みたいな色になってしまったり、ドラマチックな色になりすぎてしまったり。それを今展開しているような絶妙な色合いにするまでにはもう、ものすごく大変だったんですよね。でも職人さんはへこたれなかくて。「もう一度お願いします」というこちらの要望に応えて何度も試作してくださって。
永井 そうでしたね。この信楽焼の緋色というのは、もう1000年前からある色なんです。ただそれを現代的な方法で、ガスの釜でどんなふうに出すかというのが難しくて……。でも実は松庄さんて、それをずっとやってきていた工場さんだったんですよ。先代のときには、「緋色といえば松庄さん」と言われるほどのものを作っていた歴史があって。それが息子さんの代になり、少し作るものが変わったり、OEMで作るものが増えていった過程で、自分たちの色を忘れていた、ということなんですよね。でも私たちがショールームを見せていただいたときに、玉置さんたちがこれを見つけて、「この緋色で勝負したい」とご相談して。松庄さんも最初は「いやいや、これ難しいんですよ」と終わらせようとされていたんですけどね(笑)。でも、「難しいことにこそ、チャレンジするべきじゃないか」ということで、いろいろ横のつながりなどもフル活用して指導を受けて、挑戦し続けた結果、あの色が出せるようになったんです。
玉置 松庄さんとは、これ以外にも色々な取り組みをしてきていますが、やっぱり難しいことをやる努力をしないと到達できないもの作りがあるというか、そうでないと生み出せない付加価値というものもあると感じます。だからこそ、松庄さんとは「乗り越えたな」という実感がありますね。
永井 一緒にずいぶん頑張りましたよね(笑)。
玉置 はい(笑)。松庄さんのところのように、生産者さんのところでいろいろとお話を聞いていると、お父さんの代とおじいさんの代にはこんなことをしていた、というもの作りの歴史や系譜を伺うことがあります。キッチンツールに関わる工場さんだと、1950〜1970年代のいわゆる高度経済成長期にはたくさんの食器やキッチンツールを出荷して、「一億総中流時代」と言われた日本の食卓や台所を支えていたというところが多い。でもその後、日本人のライフスタイルや価値観が変わっていくなか、上の世代では成功したやり方が通用しない、「じゃあどうしよう」「どんな付加価値をつければいいのか」というところで悩んでいらっしゃる方が多いです。だからこそ、そんな生産者さんと、いわば生活者代表とも言える私たちが、膝を突き合わせてじっくり話し合うことはとても意味があることなのではないかと思っています。


「扱いやすいこと」だけが 価値ではないもの作りへ
玉置 今、新たに取り組んでいるもののひとつに「箸」があるのですが、その関係で先日、福井県の若狭地方の工場さんにお伺いしたのですが、そこで驚いたことがあって。その土地は若狭塗が有名ですから、さぞたくさんの漆のお箸を見られるのだろうなと思っていたのですが、どの会社さんを訪ねても、もう今は9割以上がウレタンのお箸なんです。それで、「あぁ、私たち日本人は漆を忘れてしまったのかもしれない」と衝撃を受けて……。有名な産地だった場所なのに、今は伝統工芸の世界にしか職人さんが残っていないとか、それも80代の職人さんで、という状況で。マニファクチュアとしての漆製品は、もはやほとんど作られていないことがわかったんです。
永井 漆のものって、確かに扱いが大変なんですよね。こちらが「作りたい、扱いたい」と言ってみても、「食洗機で洗えないよ、使いにくいよ」と、作っている側の方たちが言ってくる。
玉置 「かぶれるよ、売れないよ」と言ってきますよね。でもそれはなぜかと言ったら、この30、40年、もの作りを売る人たちには「食洗機で洗える」「カビない」「扱いが楽」ということを、ずっと求められていたからだと思うんです。消費者、生活者が求めるから、作る側もその条件を第一優先に考える。それでいつしか、そんな価値観が当たり前になっていって。「漆なら塗り直して使える」「陶器なら割れても直せる」ということに価値を見出す人が本当にわずかになってしまったんですね。
永井 でも本当はそれこそが日本の伝統だし、技術だし……ということなんですけれどね。
玉置 そうなんです。だからこそ、サステナブルなもの作りを考えたときに私たちはこちらの選択肢を選んでやってみたいと思っていて。「食洗機で洗える」「扱いが楽」は大切なことではありますが、それだけが良いものの価値ではないはず。すこし扱いは大変だけれど、それでも美しく、使うたびに豊かな気持ちになれる「長く使える」というものを、私たちは作ってみたいと思っているんです。